オリンピック金メダリスト:北島康介さんのコーチをされている平井伯昌さんのコラム(日経アソシエ10/20号)を読んでいたら、自閉症療育に繋がると思われるものがありました。
7月の世界水泳選手権男子50m平泳ぎで世界新を樹立したキャメロン・ファンデルバーグ選手の練習メニューを組み、メールや電話で指導をされている同氏。日本人と外国人選手の違いを目の当たりにされることも多いそう。。
なかでも一番違うのが「目的意識の持ち方」とのこと。
契約社会で生きている外国人選手は、コーチに求める役割がはっきりしていて、
目的はただ1つ 「自分が知らないテクニックや技術を補うこと」
自分にとってプラスになると思った時の食らいつきと集中力はものすごく、「強くなりたい」という気持ちを表すのが上手い。「私の指導を受けたい」と南アフリカから自費で来日する貪欲さに心を打たれ、指導にもついつい熱が入るのだそうです。
以下引用
こんなストレートな感情を目の当たりにすると「君たち(日本人)はコーチに何を求めているのか」と言いたくなる。
「平井先生に指導してもらったらきっと強くなれる。」そんな漠然とした考えだけで、目的意識もなく指導を受けても、強くなれるわけがありません。
選手は指導者に何を求めるのか
指導者は選手に何を求めるのか
それぞれの役割分担を明確にすることで、同じ練習内容でも得られるものは全く違ってくるのです。
これを自閉症療育に置き換えてみると
「○○先生(または療育施設)に指導してもらったら、きっとよくなる」 そんな漠然とした考えだけで、目的意識もなく指導を受けても成果は上がりにくい。
親は指導者に何を求めるのか
指導者は親・子どもに何を求めるのか
それぞれの役割分担を明確にすることで、同じ療育内容でも得られるものが違ってくる
そして、「よりよい状態になりたい」という気持ちを(指導者に)表すことも必要である。
ウチは複数の療育を受けていますが、その目的はまさに
「自分が知らないテクニックや技術を習得するため」
基本的に療育は「毎日の積み重ね=家庭でおこなうもの」という考えなのですが、家で何をすればいいのかが分からない。
なので、「これが良い。あれが良さそう」と聞けば、とりあえず問い合わせたり見学に行ったりして体験してみます。
1つの方法にこだわらずに試してみて、チコや我が家のスタイルに合えば、(一部分でも)家庭療育に取り入れて長く続ける。
※自閉症療育法に限らず、健常児さん向け・ビジネス向けも含めて情報収集→取り入れてみる。
保育園(学校)・療育施設・病院・公的機関など・・・それぞれとの関係性や求めるもの(目的)を明確にしておくことが重要ですね。
目的意識を持つ
 療育徒然
療育徒然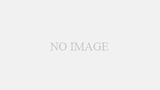
コメント