今年の冬休みは遠出しなかったので、夫婦でチコの今後についてよく話し合うことができました。療育方針をある程度固めたので、備忘録として記事にします。
---------------------------------------
広汎性発達障害と診断された当初~1年位は問題行動も「自閉症なんだから仕方ない」「これが自閉症だ」と思うのが受容だと考え、周りに対しても直接言葉にせずとも「環境を与えてくれ、教えてくれ、理解してくれ、勉強してくれ」・・と求めてばかりでした。
しかし、様々な施設・病院・講演会に行き、本を読み、ネットで検索し、実際に家庭内外で療育を行うにつれ、次のように考え方が変化してきました。
①目標管理を行う
よく「先生がきちんと対応してくれない。発達障害の事をよく分かっていない」という意見を耳にしますが、現在のような発達障害教育が表に出てきてまだ日が浅いです。
特色も個人によって千差万別。経験の少ない方に「ちゃんとやってよ。仕事でしょ!」と、責めることに終始してしまっては、せっかくのゴールデンエイジを逃してしまいます。
特に幼稚園・保育園・特別支援学級は「療育の場」ではないと思っています。
普通学級(健常児さんの環境)よりも「ある程度行動を理解して」学習(保育)環境を提供してもらえる事をラッキーと考え、先生の対応も「発達障害に対して詳しくないけれど、1人の人間としてきちんと接して下されば十分・・・更に協力して下されば万々歳!」と、思えば
成長の妨げとなる「~してくれない病」に陥る確率は低くなります。
こちらからの要望は、「目標」という型で学期毎(可能ならクオーター毎)に「今期のねらい」と「対応の例」を書き出し、それらと共に「目標達成度、現在家や療育施設で取り組んでいる内容、親の思い」を簡潔にまとめて提出し、指導の参考にして頂ければ、かゆいところに手が届きなりやすくなるのかもしれません。(親の思いが強い程枚数が多くなりがちですが、1~2ページに押さえたいところです。)
また、家庭で目標管理シートを作成し取り組みや進捗を確認することは、面倒だけどとても重要です。シートを見ながら学期毎の面談を行うと、具体的かつ核心を突く話し合いができると思います。そして的を射た話し合いを重ねるうちに、先生も生徒別の指導のコツを掴まれてくるのではないでしょうか。相手を動かすには自分から!ですね。
②必ず家庭でも取り組む
①にも通じるのですが、診断当初は「誰かの援助を受ける」ことばかり考えていました。
ところがところが・・・
「トモニ療育センター」発行の「ともに」を読むと、皆さん家庭で療育されています。もちろんやみくもにではなく、療育センターのアドバイスを受けながら。
また、コロロ 大田ステージ くれよん方式 ・・・どれもこれも「アドバイスを受けながら家庭で取り組む」ことを重要視してあります。
家庭療育を行っていなかった私は、「週2回の親子通園に通っているだけでは、やっぱり足りないんだ!」と大きなショックを受けました。
本当はこの「アドバイスしてくれる機関」が公的なものだと金銭的にかなり助かるのですが、指導力や伝える力がねぇ。。療育相談を職業とされている方には、コーチングやプレゼンの技術も磨いて頂きたいところです。
複数の療育を受け、様々な角度からアプローチするのが自閉症療育の主流である今、それを取りまとめるのは結局「親」。試行錯誤の日々は続きそうですね。
③ルールを守る/指示に従う/対応力をつけさせる
順番を守れない、自分の思いに反すると抵抗する、こだわり、ひとりごと・・・その他もろもろの困った行動を、自閉症だから「しょうがない」と思って諦めないようにしています。
だって世の中、「ダメなものはダメ!」なんですもの。
これだけ日本が世界が困窮している中、今後、自閉症・発達障害が理解され、環境が整えられる可能性は極めて低いと思います。残念ですが、大きくなればなる程その傾向は強くなるでしょう。
そうなると「少しでも適応できるように幼児期から訓練する」ことが重要となってきます。
自閉症(発達障害)の早期診断のメリットの1つとして、”「ルール」を、障害特性を踏まえた上でインプットできる”事が挙げられると思います。「障害があるから特別に配慮してもらう」のは、時として自らの首を絞めることになりかねません。
例えば「順番待ち」。以前東京ディズニーランドでは「時間の観念が希薄なため待てない」
子どものために「ゲストアシスタンスカード」という”カードを提示すれば待たなくてすむシステムがありました。(結局このシステムは悪用などもあり廃止されています。)
でもこのカードを利用するより、”TDLで他の人と同じように待つ”ことを目標に、日々練習する方がずっと有意義だと思うんです。最初は1分から練習を始め、徐々に時間を長くする・・・他の場面でも応用が効くようになりますよね。
人は初期に刷り込まれたもの程その後の刷り直しが難しい。
こだわりが強化されて、「こうあらねばならない」という思いを根強く残すと、より生きにくいものとなります。強迫観念や強迫行為まで行くと、周囲を巻き込み皆が大変な思いをします。
先のこと考えれば、「今楽する」(思い通りにさせておけば大人しい、パニックを起こさない等)よりも、苦しいけれど「物事は決まりや予定通りに動くのではなく、変化がつきものなんだよ。」「自分が嫌と思っても、この決まりには従わなければいけないんだよ」という事を、幼児期に刷り込む必要性があると思います。
この経験は「我慢できた!」「◎◎でも出来た!」という成功体験を積むことになるはず。
あと、体力的にも・・4歳児でもギャンギャン泣いて・足バタバタさせて、押さえつけるのに一苦労ですから。
とっても難しい課題ですが、
「為せば成る 為さねば成らぬ何事も 成らぬは人の為さぬなりけり」
結局「やらなければ できない」のです・・・ならば道は1つ。
やるしかない!・・・てね。
我が家の療育方針・支援の求め方/4歳8カ月時
 療育概要
療育概要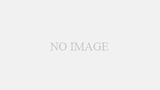
コメント
PASS: 2261dba4340be29285b1ab162ca88941
やっと諸々一段落して、このページを印刷して熟読させていただきました。
トモニ療育センター、大田ステージ、くれよん方式、それぞれチェックはしてたけど少しずつしかかじってないので、この際、総ざらいしてみようと思います。でも、私の頭で交通整理できるかな。正直、いいとこどりできる自信がないわ。ただ、ひとつのやり方にべったり依存するのは自分自身の思考停止も含めてちょっと怖いので、チコママさんみたいに「やるしかない」のかな。
コロロにはとても惹かれたので療育の先生に相談してみたら、「トムくんには合いすぎて、自主性が育たなくなるかも知れませんから、よほど慎重にしないと」と言われてしまった。うちの場合は、将来を見据えていかに主体的に生活できるかが最終目標だからと。むーん。
PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
yoshikoさん、コメントありがとうございます^^
数多くある療育方法の中から、子どもに合ったものをチョイスするのって難しいですよね。 時期によっても状態が違ってくるし。 療育って一過性のものではないので、いかに「継続」できるかもポイントだと思います。
コロロの療育が合いすぎる…という事は、トムくんは割と「人の指示に従える(ユアペース行動がある程度可能)」タイプなのかなと思いました。
チコはそこが弱い。
「パズルをしたい」と思ったら、今は絵本を見る時間だよと言っても「パズルするの!」と抵抗してしまう…ま、ある意味「自主性」はあるんだけど…そうじゃないでしょ!ってね(苦笑)
「自分の思い通りに動きたい超マイペース」タイプなので、他の人の指示でも従えるよう練習中のチコにはコロロが合ってるかな。
あ、あとね
宿題をがっつり出してくれるので「家庭療育の内容を自分で創造できない」我が家向き…でもあります。
将来を見据えるかぁ…チコの成長とともにあんまり考えなくなりました。なんか想像できなくて。。
自閉度と知的障害度が軽度ではないので、今は自立とか主体性はあんまりこだわってなくて(まだそこまで考えが及ばない…)「共存(周りの人と和やかな人間関係を作れる)」できる子になってほしいと思って、療育もそのあたりに重点を置いているかなぁ…多分。
とりあえず目先の目標設定は行っているので、それに対応しているって感じです。^^;
PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
補足です
自立とか主体性はあんまりこだわってなくて…って語弊がありますね。
1人でも生きていけるように!という強い意志ではなく、誰かの助けを借りながら生きていけるようになってほしいと思っています。もちろん就労も目指している・・・けど、具体的には何も考えていないのでありました。。。
PASS: 2261dba4340be29285b1ab162ca88941
トムはユアペース行動が少しは可能なものの、拒否できない弊害の方が大きくて、数週間後に別のかたちで荒れたりしてしまうのを繰り返してます。だから、「イヤ」「休みたい」と伝えられるようになるのが、小学校での目標かな。
だってチコくん、まだ4才だもんねえ。トムもその頃は全然人の指示が聞けなかったよ。特性は人それぞれだけど、トムの場合、気持ちが満たされて、まわりを見渡せる余裕が生まれて、はじめて次のステップにいけたのかも?と思ったり。
まずは、誰かの助けを借りながら生きていけるように愛され系をめざすっていうのは、うちも方針として同じよ。だから、幼児期はひたすら共存や愛着に力をおいて育てていけばいいんじゃないかなあ。
ただ、お子さんが成人された先輩ママによれば、大人になって愛されるという意味は、子ども時代とは若干内容が異なり、勤め先で上司の指示に素直に従え、勤勉である必要があるんだそうです。だから、学童時代から就労を意識した取り組みは必要だし、その過程で身辺や行動上の自立が不可欠になってくると。ここでの自立とは、支援抜きの自立ではなく、なんらかの道具や申し送りがあれば支援次第では自立できる、という意味ね。
先日出席した自閉症研究会でも、これでもかってくらい自立や就業準備の話が出てきて、目が点に…。それが支援学校の校長経験者や研究者からだったから余計にね。
ま、うちも、昨年後半に新しい療育に入ってから目がずいぶん開いたし。ボチボチですわ。会いたいね~。
PASS: 2261dba4340be29285b1ab162ca88941
もしよかったら、トムのお世話になってるたすくのSNS入ってみる(紹介制)?
有料だけど、親の会を毎日やってる感じで、熱心な人のブログを見るだけでも勉強になるよ。
http://tasuc.com/
ちなみに、トム家は鎌倉にございます。内緒コメで。
http://www.yn-lab.net/blog/yoshiko/
PASS: 2261dba4340be29285b1ab162ca88941
なんども失礼。メアド載せときます。
PASS: f5fac4526aadd460007e4e519984cc7d
息子が4、5歳の時。私はまだまだ飲んだくれておりました。
障がい児の親全員に、このお母さんの“気づき”が行き渡りますように。
PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
yoshikoさん
コメントありがとう!
うん、うん。全くもってその通りだと思う。
色々書きたかったので、先程メールしたよーー。
PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
cutmanさん
コメントありがとうございます。
まだまだ悩むことは多いけど、基本姿勢はここに書いた通りなんです。
でも、これを良しとされる方が沢山ではないことも実感しています。
どんなアプローチであれ、一般社会も発達障害者もお互いに歩み寄って今以上に共存できる社会になることを願い、目指しています。