今年に入ってから、このブログをご覧いただいたASD当事者の方から「自分の幼いころを思い出し、読み進めることができなかった」「幼い時は(療育者である)父が大好きだったが、成長して殺意を抱くようになった自分と息子さん(チコ)の姿が重なる」という意見を頂戴しました。
うむ。なるほど・・・確かに私も夫も自閉症スペクトラム圏内ではない(と心療内科の先生に言われた)ので、当事者の方の思考回路や感じ方を想像することが難しいです。
ウチの育児方針は「障害者としての自立を目指す」
よってチコの意思第一優先というより、思考の柔軟性を養いたいという思いが強いです。
やっぱり…かなり動揺しました。
今の育て方はチコにとって悪影響を及ぼしているのであろうか…。
でも、考えても結果は当然ながら出てきません。
無理をさせていると言われればそうかもしれません。
親の都合で1日12時間近く保育園に預けられ、帰ってきたら毎日1時間近く机に向かわされ、休みの日は毎週山歩きさせられ、行事の度に踊りやら鉄棒やら練習させられる。
チコが嫌だと言わないことをいいことに、全て親主導で「療育」という名のエゴの押付け。
こう書くと鬼畜!?
保育園の事は生活をしていく上で仕方がないことです。
私が正社員として働くことは、チコが自閉症と診断された時にリスクヘッジとして決めたことです。
家庭療育→(変化に対する適応力、コミュニケーション能力、模倣力の強化)は幼少期から練習が必要なものと感じています。
山歩き→人間の基幹は歩くことだと考えているので、やっぱり必要
行事の練習→短期の目標に向かって取り組むことは大切な経験の1つだと考えます。大勢の指示の中では出来ないことも、家庭で丁寧に復習することで多少なりとも習得できます。周りの事が見え始めた今、少しでも同調できると嬉しそうです。
ご意見を下さった方はこれらの1つ1つがどうこうというより、我が家の(育児の)傾向に警鐘を鳴らして下さったのでしょうが。。。
療育に関しては各家庭で考えが異なりますね。
このブログにコメントを下さるyoshikoさんから紹介して頂いた「森博嗣」さんのブログにこんな内容がありました。
『自殺や犯罪という破壊的結果に至った場合、その理由として、いろいろなことがクローズアップされる。しかし、そういったマイナスの理由は、ほとんど誰でもが多かれ少なかれ持っているものだ。だから、そのマイナス要因だけですぐに破滅に至るのではない。そうではなく、それに釣り合うようなプラス要因が足りなかったために、バランスを崩すのである。多くの人が普通に生きていられるのは、マイナスもあるけれど、プラスもあるからなのだ。
したがって、マイナス要因ばかりに目を向けて、たとえそれを逐一排除できたとしても、たぶん問題は解決しない。(中略)おそらく、プラスが不足している人は、1つのマイナスが消えても、すぐに新しいマイナスを見つけてきて、落ち込んでしまうだろう。
(抜粋)夫婦仲が悪く、仕事も上手くいかなくて、借金、子供には見放され、友達もいない、もう駄目だと思い詰めている人が、たとえば子犬を一匹飼うだけで、一時的にでも問題が解決するかもしれない。この「一時的」が大事である。生きるということは、そういうものだと感じている。』
すごいですね。
正にその通りだと思います。
療育をしている場面だけを見ると、チコを破滅に向かわせるように感じるかもしれませんが、プラスの要素もたくさんあるのです。
保育園の先生型は本当によくチコを可愛がって下さいます。
療育的なことは別としても、自閉症だと認識して「人」としてきちんと扱ってもらえれば私は満足なのです。
療育の先生にも恵まれ、仲のよい(?)両親や祖父母に囲まれています。
私が幼少期に「こんな家庭だったらいいな」と思っていた環境にほぼ近い位置にいます。
正直、うらやましい。
・・・ちょっと感情論的すぎかな。
要はチコには普段の生活の中で楽しいことがたくさんあると思うのです。
療育をしている姿は生活のほんの一部分であるということ。
心が崩れそうな時は支える環境は比較的整っている(のではないか)ということ。
前出の森さんのブログからもう一文。
『若いうちに挫折を味わうべきだ」という発言も聞かれるけれど、好き好んで挫折を味わう必要はない。失敗覚悟で大きなチャレンジをするよりは、少しずつでも成功を積み重ねた方が良いに決まっている。もし、最終目標を諦めたくなかったら、方法、時期など、ほかのすべてに対して妥協する柔軟性を持つべきだ。』
療育テーマのヒントになりますね。
我が家の早期療育の是非
 療育徒然
療育徒然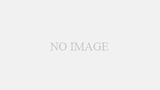
コメント
PASS: 2261dba4340be29285b1ab162ca88941
わたしもチコくんのスケジュールを見て目が点になった1人だけど、どの程度負荷をかけるべきかは子どもの性格によるから、マニュアルはないはず。療育が様々あるというより、子どもの個性が様々だから、その数だけ療育がある、ということだと思います。
障害の有無に関わらず、いかに子どもを観察し、子どもの心に寄り添って生活していくか。子どもの心に共感しつつ、人生の先輩としてどのように道を照らし続けるか。親や周囲の大人が自問自答しながら育てていく中にこそ、答えはあるんだと思います。
私自身は、親の中の一貫性と、その一貫性を子どもの状態に合わせて壊せる柔軟性の整合をとるのが、究極の目標かな。
そして、森さんの姿勢から読み取るべきは、とりもなおさず、「自己肯定感」や「根拠のない自信」をいかに育てるか、に尽きるんではないかと思います。相手の発言を自分への攻撃とは捉えず、そういう意見もあるんだ~とスルーできる心、ってことです。スマートな防御は、人生における最大の武器になるかと。
(私の母も、祖母にずっとチクチクやられてきたから、ちょっと何か注意すると、自分を全否定されたように感じるらしく、すぐカッとなるの…大変よ。あれは、祖母が悪いわ)
長文失礼。
PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
コメントありがとうございます。
ね、ウチの取り組みって目がテンになる程!?
ゴメン。嫌味でも何でもなくホントに疑問。。。なんせ時間のない家庭なので、沢山やってる意識がなくて・・・
スマートな防御・・・はい。しかと心得ました^^
ただ、最近よく見かける「療育の弊害」。読みながら「何でもかんでも療育のせいじゃないよな~」なんて思っています。 ハッ!心得が・・・
PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
この記事をご覧いただいている方へ
スミマセン。この記事は9/9にパスワードを掛けさせて頂きます。
PASS: 2261dba4340be29285b1ab162ca88941
いや、まあ、うちが相当のんきだからねえ。でも、やらない勇気ってのもあると思うのよ。
メールするわ。