ゆうゆうセンター開設1周年記念講演会の議事録です。
大急ぎでメモを取ったので途中自分なりの解釈となった部分があると思いますが、ご了承下さい。2人講演されたので、「1」「2」で分けています。
----------------------------------------
福岡市発達障害者支援センター開設1周年記念講演会
「自閉症の人にとっての心地よい生活づくり」
※ASD=自閉症スペクトラム(様々な知能・現れ方をする自閉症全ての総称)以下ウィキペディアより引用
自閉症は症例が多彩であり、健常者から重度自閉症者までの間にははっきりとした壁はなく、虹のように境界が曖昧であるため、その多様性・連続性を表した概念図を自閉症スペクトラムや自閉症連続体などと呼ぶ
※「それいゆ」=日本自閉症協会佐賀県支部を母体として発足したNPO法人。障害児・者を持つ親への教育相談・支援 (コンサルテーション)を行う。 代表:服巻智子氏
■講演者 1【榎木たけこ氏】
◎プロフィール
幼少期より「変った子」と言われ、友達はいなかった。
社会性に問題はあったものの、知的な遅れはなかったので保育園~大学院(大学・大学院とも2校づつ卒業)まで全て普通学級に在籍。大学院時代にASD(自閉症スペクトラム)と診断される。
現在、それいゆ自閉症支援専門家.養成センター研究員として就業中。
◎生育歴
保育園時代は言葉がほとんど出ておらず、クラスメイトがどんなに話しかけても無言(無視)だったので、お迎えにきた母親に告げ口や文句を言う事もあった。(コミュニケーションはほとんどとれていなかった)
小学生になってから言葉はでてきたものの、社会性はほとんどなく、クラスでも一匹狼。誰がどうなろうと関心がなかった。しかし、彼女の奇妙な行動・友達と遊ばない事などに対して、両親及び周りの大人たちは怒ったり、責めたりする事がなかった為、それが変だという自覚や焦りもなく、むしろ「変った子」=誉め言葉と感じていた程だった。
また偏食も激しかったが、母親(栄養士)は「栄養がとれていれば良い」という考えで、嫌いな食べ物の代替品を用意し無理強いをさせなかった。この偏食は成長と共に緩和していく。このように幼少期に両親に「周りと同じになる事」を強要されなかった為、のびのびと自尊心を失わずに成長した。
普通小学校→高校→大学(教育学を専攻)と進学し、勉強はよくできていた。しかし、就職活動をするタイミングが分からず(本人曰く、誰も教えてくれなかった。また、周りの雰囲気で察知する事もできなかった)、気付いた時には時期を逸していた為、大学院へ進学する。
学生時代にアルバイト歴あり。(「郵便局(1年)」「映画館(半年)」「水族館(短期)」など) 慣れるまでに時間はかかったが、慣れてしまえば(映画館以外)仕事は楽しかった。退職理由は引越し等が主で円満退社であり、人間関係でのトラブルではなかった。業務では郵便局での「仕分け」作業が天職だと感じた。
(服巻先生は、彼女の学歴が高いため郵便局には就職できなかっただろうと言われていた。)
◎ASDと診断される過程
最初にASDを疑ったのは、大学院の頃。同級生がADHDの研究をしており、そのチェックリストを皆でしていたら自分はほとんどにチェックが入っていた。
更に次の大学院で受診をすすめられたので、センターへ行くと「ASD」だとすぐに診断を下された。
自分が診断され、弱いとされる部分を意識しはじめると周りが見え出し、状況が分かるようになり苦しむ事もでてきた。(しかしそれは成長の証である。)
◎就職への道
2つ目の大学院在籍中、またもや就職活動に乗り遅れそうな中、自身のHP(内容はASDや専攻分野)を通して、「それいゆ」代表の服巻先生と出会い、「就職が決まってないなら、ウチで働いてみる?」と誘われて佐賀へ。
服巻先生は「榎木さんは完璧な自閉症。私が小さい頃の彼女に会っていたら、5分で診断できたと思う。」と言われ、また「早期診断を受けていない(療育を受けていない)成人ASDで、こんなに状態のよい人はめずらしい」とも言われていた。
(早期診断されずに成長した成人ASDの中には、長年の不適切な叱咤や行動強制、いじめによって、自閉の障害そのものより更に困難な二次障害・三次障害を抱える人が少なくない。)
◎就職に際してサポートしてもらったところ
・コピー機使用持、電圧が下がる事で起きる電灯の点滅を改善(電圧変更工事を実施)
・自分の席の周りをパテーションで囲う(本人がコクヨのNO.というように品番指定してきた)
・通院をしているので有給の枠以外での休暇の設定(現在は有給の範囲内で休んでいる)
・誰に相談していいのか分からないので、相談する人を決めておく(相談窓口の設定)
・突然の変化に弱いので、スケジュールの変更・部署異動などは事前予告する(心構えができていれば何とか対応できる)
・朝の出勤を通常より2時間、退勤を1時間遅くし、皆より労働時間を1時間短縮する
・環境の変化で本人が何もできなくなる状態になったら(食事も摂らずにじっと固まる事もある)業務命令として食事を摂らせる(ウィダーイン・ゼリーを目の前で飲ませる等)
・業務の中に「夕方の散歩」を入れて、常に気分転換やリラックスできる環境を用意する
◎社会人として働いてみて
【困難な部分】
・変化に弱いので「物がなくなる」「人の席が替わる」「部署のメンバーが変る」等、
いつもと違う感じだと何もできなくなる。
・気分的に下がると仕事に影響する
(嫌だという気持ち、何に対して困難を感じるのかは、その事柄があって2・3日後にしか
分からず、そこから落ち込み、気分が下がる。タイムラグがある)
・見えない部分での違和感
・上司、同僚、同じ部署の人の認識がしにくい。人の名前と顔を覚えるのが苦手。
【服巻先生より】
榎木さんは就職してから社会性が7歳を越えた。障害を本人が自覚するという事は困難を伴う事も多いが(例えば異動による席替え)、それは今まで関心がなかった周りの事が見えてきたという事である。また、彼女は働きはじめて初めて「人と別れて寂しい」という感情が出てきた。とても良い事です。
会社側がサポートする事によって安定した環境が整うと本人の仕事能率が向上し、会社にとっても本人にとっても有益です。ちなみに榎木さんは乗り物が大好きなのですが、今回は佐賀から福岡に来るにあたり、地下鉄や電車に乗れる事をとても楽しみにしていました。こだわりは特に青年期以降に本人の「癒し」となりますので、無理に取り上げる事なく、上手に付き合っていってください。
ASDの人は自分が相手の気持ちを理解することは困難だが、自分のことを相手に人一倍分かってほしいと思っている。(この矛盾した部分が障害で、厄介なところ)また、相手が自分のことをどう思っているか直感で分かる。
※講演会では出てきませんでしたが、現在はこの困難な部分をプレイセラピーで「遊び」を通して身に付けさせようという動きがある。それまでプレイセラピーは自閉症に効果がないと言われていたが、近年また見直され「考えながら作業するという能力は遊びでしか身につかない」「良く遊べる子供はよくのびる」「遊びを通して譲り譲られる・順番の概念を学ぶ」という考えのもと、行動面(ABAなど)だけではなく、心の療育(プレイセラピー)との両立が必要とされている。
◎他のASD成人の現状
・ジョブマッチングの難しさ。
「やりたい仕事」と「できる仕事」は別なのだが、自分の事を客観的に評価できないので、
アドバイスを必要とする
・自分で計画をたてられないので、締め切りを守る事も困難。業務自体はできるので、
スケジューリングサポートを要する。
・電話を掛けたり、受けたりという事も事前の心構えが必要。
また同時に2つ以上の事が出来ないので、電話の内容メモをとる事が難しい。
・ヒソヒソ声など、色々な音があると気が散りやすい
◎サポートがあると助かる部分
【行政指導として】
・仕事を決める際の客観的な評価
※本人が知らない職種や職業スキルの紹介。障害特性でできる・合う職業を客観的に
評価してもらい、その結果をもとに相談できる体制)
・職場への障害表明(第三者が行う方が上手くいく)
【職場に対して】
・物理的なサポート(共有品だといつ使っていいのか分からないので、個人貸与にする。
(自分の場所を確保する等)
・1つの方法に固執する場合があるので(その方法しか思いつかない)、他の方法があれ
ばアドバイスする
・どんな些細なことでも話を聞いてくれる人と場所の確保
◎総体的にみて
ASDの特性として「実行機能障害」がある。その事柄自体のスキルはあるのだが、それを「やるタイミング」が分からない。(話しかけるタイミング、共用品を使うタイミングetc・・・)また、計画に従えても、立てることはできない。これらに対しての訓練やサポートがあると、随分と違ってくる。
今後は職業訓練の機会を増やす事を望む。
普通の人は生活の中で自分の適性を読み取る事ができるが、ASDは突然仕事を決める事は難しい(やってみないとわからない)ので、できれば中学・高校から障害特性を考慮に入れた職業訓練を受け、将来に備えてはどうか。
また、子供は親の希望を(薄々ながらも)感じ取るので、「◎◎の仕事がいい、△△の仕事は嫌」と親が思うと従ってしまいがちになる。そして、それがこだわりになり、その(親の希望する)職業以外は受け付けない状況となってしまい、職業のミスマッチや自分の可能性・選択を狭めてしまう事に繋がる。
できるだけニュートラルな状態でジョブトレーニングを受けられるように、親のエゴを植えつけない。
福岡市発達障害者支援センター開設1周年記念講演会 議事録1
 講演会レポ
講演会レポ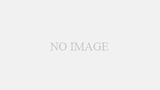
コメント